——2013年の振り返りをお願いします。
宇陀社長 当社は2013年、グローバル市場と日本市場の両方で前年比30%強の売り上げ増を実現できました。日本の景気が回復基調に乗ったという一面もありますが、それだけが全ての要因ではありません。当社は2011年から3年連続で業績を拡大しており、景気変動にあまり左右されることなく順調に売り上げを拡大しています。
その理由として1つ言えるのは、企業向けクラウドサービスというビジネスモデルがまだ新しいものだということです。クラウド市場はいわば“発展途上”であり、これから利用が拡大していくホワイトスペースがたくさんあります。そこにうまく食い込めているのが、当社の大きな成長要因と言えるでしょう。
ただし、クラウドがもたらす「所有から利用へ」という変化は、何もいま始まったばかりのものではありません。建築に例えれば、自社ビルを保有している企業が現在どれだけあるでしょうか? 自ら重厚長大な資産を持つのではなく、必要な分だけ利用したほうが効率がいいという“常識”が、今になってようやくITの世界にも浸透しつつあるのです。
その上であらためて2013年の事業に関して言えば、日本企業のクラウドに対する認知がこれまで以上に広がり、クラウドに対して慎重な考えを持っていた製造業なども活用に向けて動き始めました。その多くはまだ試行段階ではありますが、今まで“自前主義”を貫いていた企業もクラウドの重要性を大きく認識し始めた1年だったと感じています。
——2013年に苦戦したこと、特に成果を上げたことをそれぞれ教えてください。
宇陀社長 まず大変だったことは、他社のサービスも含めて「クラウド」とひとくくりに評価されてしまいがちな中で、いかに顧客の信頼を獲得するかということです。
企業が本格的にクラウド導入を検討する際、当然セキュリティ対策などが評価項目となります。そうした中で万一、他社のクラウドサービスで情報漏えいなどの事故が起きてしまうと「クラウドは不安」という漠然としたイメージが市場に広がってしまいます。そこでいかに「セールスフォースのクラウドなら安心」と思ってもらえるかに苦心しました。
裏を返せば、2013年は「信頼」に関してさまざまな取り組みを進められた1年でもあります。その1例を挙げれば、日本銀行出身者に金融プロジェクト担当アドバイザーに就任してもらったほか、日本郵政の元社長に企業顧問に就任してもらいました。彼らももちろん、当社を「信頼できる企業だ」と評価しているからこそ協力してくれているのです。
こうした信頼のための取り組みは、今後じわじわと成果を上げていくことでしょう。特に、金融業や製造業などが本格的にクラウド導入を進める上で、サービスや運営会社の信頼性はとりわけ大きな比較検討要素になるはずです。
——2014年の事業目標を教えてください。
宇陀社長 当社は近い将来、日本市場での単年度売り上げ1000億円を突破することを目標としています。2014年はそれに近づくため、これまで以上に中小規模のパートナー企業や各種業界団体との連携を強化していきます。また、中小企業庁と共同で実施している中堅・中小企業のサポートプログラム「ミラサポ」も絶対に成功させる所存です。
単年度で売り上げ1000億円を目指すといっても、当社はクラウドの会社ですから、特定顧客からの売り上げをその年に一括計上するわけではありません。その翌年も翌々年も継続してサービスを使っていただくことで、実質的には売り上げ5000億円くらいの価値になると見込んでいます。
こうしたビジネスモデルによって可能になるのが、研究開発に対する継続的な投資です。クラウドサービスの特徴として、顧客がいつでも利用をスタートでき、いつでも終わらせられるということが挙げられます。そのように顧客に自由を与えつつ継続的に利用してもらうためには、日々の研究開発を怠らずにサービスの品質を高めていくことが欠かせないのです。
——最後に、宇陀社長が「組織を率いるリーダー」として絶対に譲れないことをお聞かせください。
宇陀社長 自分に対しても他の社員に対してもそうですが、セールスフォース・ドットコムという会社の評判や信頼を落とすことだけは絶対に許せません。
私が2004年に当社の社長に就任してから約10年にわたって築いてきた信頼も、たった1人が起こした不祥事によって失われてしまうこともありえます。もし自分が仕事において激怒することがあるとすれば、社員が当社の信頼を損ねるようなことをした時でしょう。
一度失ってしまった信頼を取り戻すことは簡単ではありません。私自身も普段から言動に気をつけていますし、社員に対する働きかけも積極的に行っています。これからもずっと、お客様からの信頼第一でビジネスを展開していきたいと強く思っています。
関連記事
- Image may be NSFW.
Clik here to view.![「日本のLINEはすごい」とセールスフォースのベニオフCEO、自社サービスにも「参考にした」]() 「日本のLINEはすごい」とセールスフォースのベニオフCEO、自社サービスにも「参考にした」
「日本のLINEはすごい」とセールスフォースのベニオフCEO、自社サービスにも「参考にした」
salesforce.comの企業向けモバイルプラットフォーム「Salesforce 1」は、日本のメッセンジャーアプリ「LINE」を参考に開発。ベニオフCEOは「LINEほどうまく機能しているサービスはない」と話す。 - Image may be NSFW.
Clik here to view.![企業を“モバイルレディ”に変える「Salesforce 1」、ベニオフ氏が発表]() 企業を“モバイルレディ”に変える「Salesforce 1」、ベニオフ氏が発表
企業を“モバイルレディ”に変える「Salesforce 1」、ベニオフ氏が発表
salesforce.comの年次カンファレンス「Dreamforce 2013」が開幕。初日の基調講演では、企業のモバイル活用を支援する新プラットフォーム「Salesforce 1」をベニオフCEOが初披露した。 - Image may be NSFW.
Clik here to view.![“箱売りはダメ”から卒業? セールスフォースがHPと組んだ理由]() “箱売りはダメ”から卒業? セールスフォースがHPと組んだ理由
“箱売りはダメ”から卒業? セールスフォースがHPと組んだ理由
「箱を売るのはクラウドではない」と主張してきたsalesforce.comが、HPの垂直統合型ITインフラを活用した新サービス「Salesforce Superpod」を発表。その狙いとは——。 - Image may be NSFW.
Clik here to view.![セールスフォース・ドットコム 代表取締役社長 宇陀栄次氏——「歴史に学べ!」先駆者が語る“IT産業の未来”]() セールスフォース・ドットコム 代表取締役社長 宇陀栄次氏——「歴史に学べ!」先駆者が語る“IT産業の未来”
セールスフォース・ドットコム 代表取締役社長 宇陀栄次氏——「歴史に学べ!」先駆者が語る“IT産業の未来”
CRMをオンデマンドで提供するサービスを展開するセールスフォース・ドットコムが急成長を遂げている。ソフトウェアをサービスとして提供する「SaaS」ビジネスの先駆者として、世界中で顧客を急増させている。企業の業務システムの利用形態を根本から変革させる可能性を持つ同社のビジネスの仕組みはいったい何が違うのか。
Copyright© 2013 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.











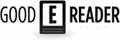
































![Microsoft Windows ストア ギフトカード 5000円 [パッケージ] (Windows 8.1 / Xbox 360で利用可)](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41-z7UgNhjL._SL75_.jpg)
![Microsoft Windows ストア ギフトカード 2000円 [パッケージ] (Windows 8.1 / Xbox 360で利用可)](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41awY0SPhiL._SL75_.jpg)
![Windows ストアギフトカード 4,000 円 (Windows 8.1/Xbox 360で利用可) [オンラインコード] [ダウンロード]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41b%2BkM%2BWcCL._SL75_.jpg)
![マイクロソフト Surface 2 32GB 単体モデル [Windowsタブレット・Office付き] P3W-00012 (シルバー)](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31%2BEHy56lzL._SL75_.jpg)

![マイクロソフト Surface Pro 2 512GB 単体モデル [Windowsタブレット・Office付き] 77X-00001 (チタン)](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31iMC7Yj%2B9L._SL75_.jpg)



























































































































































































































Facebookコメント