2013年夏モデルとしてウィルコムが発売した京セラ製の「DIGNO DUAL 2 WX10K」(以下、DIGNO DUAL 2)は、ウィルコム端末として初めてPHSと3G/4Gの2つの通信方式に対応した“デュアル”モデルだ。
DIGNO DUAL 2は2012年に同じくウィルコムが発売した「DIGNO DUAL WX04K」(以下、DIGNO DUAL)の後継機であり、ウィルコムスマートフォンのフラッグシップモデルという位置付け。DIGNO DUALは、PHSによる音声通話のほか、ソフトバンクモバイルの3G網を使う音声通話とパケット通信に対応していたが、DIGNO DUAL 2では新たにソフトバンクモバイルの4G通信(AXGP)にも対応した。
ウィルコム同士であれば24時間無料となるPHSの音声通話と、それ以外の携帯電話や一般固定回線にも定額通話が行える「だれとでも定額」に加え、月額のパケット通信料が2980円になる新料金プラン「ウィルコムプランLite」も利用できる。
OSはDIGNO DUALのAndroid 2.3からAndroid 4.2に進化し、操作性なども大幅に改善された。プロセッサーは1.5GHzデュアルコアのMSM8960を採用。ディスプレイは4.7インチのHD(720×1280ピクセル)TFT液晶を搭載し、おサイフケータイ、テザリング、防水(IPX5/IPX7)/防塵(IP5X)性能、ワンセグ、赤外線通信など日本向け機能を詰め合わせたまさに“オールインワン”スマホだ。
そんなDIGNO DUAL 2について、商品企画を担当した京セラ 通信機器関連事業本部 マーケティング部 商品企画課の川居伸男氏と、デザインを担当した同社デザインセンター デザイン4課の三田真由氏に話を聞いた。
なるべく安くスマホを使いたいに人にメリットある端末を
川居氏は、DIGNO DUAL 2について「ウィルコムが提供する『だれスマ』(新料金プランのキャンペーン)を活用したいユーザー向けに開発したもの」と話す。ウィルコムは2013年夏モデルの発表会で「スマホ戦国時代に参戦」することを表明。料金面はもちろん、端末の性能面でも、携帯電話キャリアのスマホと戦えるラインアップを目指した。その中でDIGNO DUAL 2は、DIGNO DUALにはなかった下り最大76Mbpsの4G通信に対応したことが大きなセールスポイントになる。
「メインユーザーとして想定したのは、コスト意識が高い30代〜40代男性で、スマホの利用料金を下げたいユーザー全てが対象です。1Gバイトという制限はありますが、通話だけでなくパケット代も安く済ませたい人には、通信速度の速さと合わせて非常にメリットのある端末です」と川居氏。スマホ料金の高さを気にするユーザーを取り込みたいウィルコムの要望に応える形で、開発が始まったという。
それでは京セラは、夏モデルの中でDIGNO DUAL 2をどう位置付けているのだろうか。川居氏は「私たちは最新のデバイスを盛り込んでハイスペックさを狙うというより、スマホの裾野を広げる役割を担っています。ウィルコムの中ではフラッグシップモデルですが、一番は使いやすさを重視して開発しました。ユーザーの中には初めてスマホを使う人も多いと想定していましたし、実際にそのようです」と話す。
京セラ製スマホでは、ソフトバンクモバイルが2013年夏モデルとして発売した「DIGNO R 202K」もAXGPの4G通信(SoftBank 4G)に対応しているが、もちろんこちらはPHS通話には対応していない。しかしDIGNO Rは幅60ミリで重さ約94グラムの軽くてスリムなボディが特徴で、もしこのサイズ感でPHS対応のスマホが生まれれば、小柄な端末に慣れ親しんだウィルコムユーザーにとっては、乗り換え候補のスマホとして魅力的だ。
川居氏はこれからのラインアップについて、「今後はウィルコム端末でもDIGNO Rのようなコンパクトな端末を検討したいです」と答えてくれた。将来的に、PHS通話と3G/4G通信を融合したコンパクトモデルが出ることを期待したい。
4G+PHSの“ニコイチ”を実現する難しさ
DIGNO DUAL 2の開発では、PHSと3G/4G通信を両立させる技術的な難しさもあったと言う。「今回Qualcommのチップセットを使いましたが、同社の協力もあってPHSをサポートするベースバンドチップを搭載できました。また、(4G対応により)DIGNO DUALからアンテナが2本増えたので、その配置や電波の干渉など考慮すべき面が多く、綿密なシミュレーションも行いました。端末のエッジ部分にはほとんどアンテナが入っているので、握っても感度が落ちないレイアウトにするなど工夫しています」と川居氏は苦労を語る。
PHSと3G/4G通信という2つのシステムを組み合わせる“ニコイチ”の実装についても「Qualcommのチップセットも、OSのAndroidも、もともとはPHSに対応していません。これに新しいシステムを追加するわけですから、手間暇かけて進めました。もちろん、ユーザーにとっては遜色ない使い勝手になっています」と川居氏は振り返る。
今回DIGNO DUAL 2に追加された機能に、PHSの電話番号宛てに短いメッセージを送受信できる「ライトメール」がある。DIGNO DUALでは、開発期間の問題もあり実装できなかった機能で、ユーザーからの要望も多かったようだ。
「多くのウィルコムユーザーが重視する機能なので、DIGNO DUAL 2ではぜひ対応したいなと。ライトメールはパケット通信ではなく音声通話の仕組みを使う点は3GのSMSに近いですが、SMSはあくまでサーバー型のサービスです。ライトメールはダイレクトなレスポンスなど、“つながる”便利さを体験できると思います」と川居氏は話す。
技術面で手間と苦労がかかっているDIGNO DUAL 2だが、市場全体ではニッチなウィルコム端末でそれだけのコストに見合うだけの売上げが期待できるのか? という疑問もある。
その点について川居氏は、「当然ながらビジネスなので、採算の取れないものは開発しません。リソースを効率的に活用しながら、ウィルコムの事業に貢献させていただいてます」と説明する。ウィルコム夏端末のフラッグシップモデルという位置付けなだけに、定額通話だけでなく4Gの高速通信を楽しみたい、またスペックの高さや機能の多さに期待するウィルコムユーザーも少なくない。コスト面を重視しながら、できる限りの作り込みがなされたようだ。「(京セラは)国内より海外向けモデルの部品供給のほうが多いので、そことのシステム共有や調達面でのスケールメリットがあります。スマホは共用できる部品が多いので、全体で効率化を図っています」(川居氏)と、グローバル展開でほかの国内メーカーと差別化できていることを明らかにした。
関連キーワード
DIGNO DUAL WX04K | ウィルコム | DIGNO DUAL 2 WX10K | PHS | スマートフォン | 通信 | 京セラ | Android | パケット定額 | ソフトバンク | フラッグシップ | だれとでも定額 | Android 4.2 | 開発陣に聞く | QUALCOMM(クアルコム) | ユーザーインタフェース
関連記事
![ウィルコム、PHS通話+4G通信対応の「DIGNO DUAL 2 WX10K」を7月18日に発売]() ウィルコム、PHS通話+4G通信対応の「DIGNO DUAL 2 WX10K」を7月18日に発売
ウィルコム、PHS通話+4G通信対応の「DIGNO DUAL 2 WX10K」を7月18日に発売
ウィルコムは、京セラ製のAndroidスマートフォン「DIGNO DUAL 2 WX10K」を7月18日に発売する。PHS通話とSoftBank 4Gに対応し、防水/防塵性能やおサイフケータイなども備えた。![ウィルコム、PHS通話+4Gの高速通信に対応した「DIGNO DUAL 2 WX10K」を発表]() ウィルコム、PHS通話+4Gの高速通信に対応した「DIGNO DUAL 2 WX10K」を発表
ウィルコム、PHS通話+4Gの高速通信に対応した「DIGNO DUAL 2 WX10K」を発表
ウィルコムは、京セラ製のAndroidスマートフォン「DIGNO DUAL 2 WX10K」を7月18日に発売する。PHS通話のほか、SoftBank 4Gに対応して下り最大76Mbpsの高速通信が利用できる。おサイフなどの便利機能も搭載した。![「LCCとして、大きなニッチを狙う」——ウィルコムのスマホ・PHS戦略]() 「LCCとして、大きなニッチを狙う」——ウィルコムのスマホ・PHS戦略
「LCCとして、大きなニッチを狙う」——ウィルコムのスマホ・PHS戦略
ウィルコムが7月4日、新商品/サービス発表会を行った。7月1日に更正手続を完了し、ソフトバンク子会社となったウィルコム代表取締役社長の宮内謙氏は、「LCC(ローコストキャリア)として、これからも大きなニッチを狙っていく」と宣言した。![ウィルコム、PHS+4G対応スマホや他社Androidでも“だれ定”が使えるBT端末などを発表]() ウィルコム、PHS+4G対応スマホや他社Androidでも“だれ定”が使えるBT端末などを発表
ウィルコム、PHS+4G対応スマホや他社Androidでも“だれ定”が使えるBT端末などを発表
ウィルコムが2013年夏モデルを発表。PHSと4Gに対応した「DIGNO DUAL 2」、シャープ製のPHSスマホ「AQUOS PHONE es」に加え、他キャリアのAndroidでも“だれ定”が利用できるBluetoothアダプターなどをラインアップした。![世界初の「PHS対応Androidスマートフォン」 開発の舞台裏を京セラに聞く]() 世界初の「PHS対応Androidスマートフォン」 開発の舞台裏を京セラに聞く
世界初の「PHS対応Androidスマートフォン」 開発の舞台裏を京セラに聞く
ウィルコムから発売された京セラ製の「DIGNO DUAL WX04K」は、世界で初めてPHS通話に対応したAndroidスマートフォンだ。今、なぜPHSなのか、そして開発にはどんな苦労があったのか。京セラに聞いた。![「だれとでも定額」が当面無料:24時間話し放題のPHS+3G対応スマートフォン——「DIGNO DUAL WX04K」登場]() 「だれとでも定額」が当面無料:24時間話し放題のPHS+3G対応スマートフォン——「DIGNO DUAL WX04K」登場
「だれとでも定額」が当面無料:24時間話し放題のPHS+3G対応スマートフォン——「DIGNO DUAL WX04K」登場
ウィルコムのPHSとソフトバンクの3Gに対応したスマートフォンが発表された。「DIGNO DUAL」は専用プランや「だれとでも定額」で通話し放題になるほか、月額5460円のパケット定額サービスを利用できる。
Copyright© 2013 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.



 ウィルコム、PHS通話+4G通信対応の「DIGNO DUAL 2 WX10K」を7月18日に発売
ウィルコム、PHS通話+4G通信対応の「DIGNO DUAL 2 WX10K」を7月18日に発売 ウィルコム、PHS通話+4Gの高速通信に対応した「DIGNO DUAL 2 WX10K」を発表
ウィルコム、PHS通話+4Gの高速通信に対応した「DIGNO DUAL 2 WX10K」を発表 「LCCとして、大きなニッチを狙う」——ウィルコムのスマホ・PHS戦略
「LCCとして、大きなニッチを狙う」——ウィルコムのスマホ・PHS戦略 ウィルコム、PHS+4G対応スマホや他社Androidでも“だれ定”が使えるBT端末などを発表
ウィルコム、PHS+4G対応スマホや他社Androidでも“だれ定”が使えるBT端末などを発表 世界初の「PHS対応Androidスマートフォン」 開発の舞台裏を京セラに聞く
世界初の「PHS対応Androidスマートフォン」 開発の舞台裏を京セラに聞く 「だれとでも定額」が当面無料:24時間話し放題のPHS+3G対応スマートフォン——「DIGNO DUAL WX04K」登場
「だれとでも定額」が当面無料:24時間話し放題のPHS+3G対応スマートフォン——「DIGNO DUAL WX04K」登場





















![マイクロソフト Surface Pro 128GB [Windowsタブレット・Office付き] 5NV-00001](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31pYzurc40L._SL75_.jpg)


 Windows 8.1は10月17日公開
Windows 8.1は10月17日公開 BUILD 2013:「Windows 8.1 Preview」ファーストインプレッション──バックエンドでの細かい変更が目立つ
BUILD 2013:「Windows 8.1 Preview」ファーストインプレッション──バックエンドでの細かい変更が目立つ BUILD 2013:「Windows 8.1」詳細機能を公開──バルマー氏基調講演フォトリポート
BUILD 2013:「Windows 8.1」詳細機能を公開──バルマー氏基調講演フォトリポート 「Windows 8.1 Preview」のダウンロード提供開始
「Windows 8.1 Preview」のダウンロード提供開始 本田雅一のクロスオーバーデジタル:Windows 8.1はMicrosoftの課題にどう挑むか
本田雅一のクロスオーバーデジタル:Windows 8.1はMicrosoftの課題にどう挑むか 鈴木淳也の「まとめて覚える! Windows 8」:スタートボタンが復活──「Windows 8.1」はどこが変わるのか
鈴木淳也の「まとめて覚える! Windows 8」:スタートボタンが復活──「Windows 8.1」はどこが変わるのか Windows 8特集
Windows 8特集 「Windows 8.1(コードネーム:Windows Blue)」は無料アップデートと正式発表
「Windows 8.1(コードネーム:Windows Blue)」は無料アップデートと正式発表 “なんだかメンドー”を解消する「Windows 8便利ショートカット」7選
“なんだかメンドー”を解消する「Windows 8便利ショートカット」7選 日本マイクロソフト、Windows 8用の“Windowsボタン”を備えたモバイルマウス「Sculpt Mobile Mouse」
日本マイクロソフト、Windows 8用の“Windowsボタン”を備えたモバイルマウス「Sculpt Mobile Mouse」 特集「Surface RT」の“ここ”が気になる:第1回 内蔵型スタンド“Kickstand”はアリか?——「Surface RT」
特集「Surface RT」の“ここ”が気になる:第1回 内蔵型スタンド“Kickstand”はアリか?——「Surface RT」 注目タブレットデバイス情報はここから:タブレット USER
注目タブレットデバイス情報はここから:タブレット USER 次世代PCデータ通信特集
次世代PCデータ通信特集 URLを入力し、「チェック開始」のボタンを押す
URLを入力し、「チェック開始」のボタンを押す

 ColorSelector
ColorSelector 第一色覚(赤)
第一色覚(赤) 第二色覚(緑)
第二色覚(緑) 第三色覚(青)
第三色覚(青)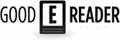

 電子書籍エージェンシーモデル訴訟、米連邦地裁「Appleは有罪」
電子書籍エージェンシーモデル訴訟、米連邦地裁「Appleは有罪」 米司法省の電子書籍エージェンシーモデル訴訟、3日目でついにAppleとAmazonが対決
米司法省の電子書籍エージェンシーモデル訴訟、3日目でついにAppleとAmazonが対決 「電子書籍の価格つり上げを主導」 Appleが独禁法違反、米地裁が判断 ジョブズのメールも証拠に
「電子書籍の価格つり上げを主導」 Appleが独禁法違反、米地裁が判断 ジョブズのメールも証拠に 知識を得るということはやっぱり読書、万物が流転しても
知識を得るということはやっぱり読書、万物が流転しても













 AXGP+LTE対応の「Pocket WiFi 203Z」「Pocket WiFi(GL09P)」、8月9日発売
AXGP+LTE対応の「Pocket WiFi 203Z」「Pocket WiFi(GL09P)」、8月9日発売 ずっとおトク割で月3880円に:イー・アクセス、下り最大110Mbpsの「EMOBILE 4G」を8月上旬以降に開始
ずっとおトク割で月3880円に:イー・アクセス、下り最大110Mbpsの「EMOBILE 4G」を8月上旬以降に開始 イー・アクセス、ソフトバンクデータ通信にも対応するモバイルWi-FiルーターとUSBデータ通信端末を発表
イー・アクセス、ソフトバンクデータ通信にも対応するモバイルWi-FiルーターとUSBデータ通信端末を発表 EMOBILE 4G-S対応:「EMOBILE 4G-S」対応のハイスペックな防水スマホ「ARROWS S(EM01F)」、8月20日発売
EMOBILE 4G-S対応:「EMOBILE 4G-S」対応のハイスペックな防水スマホ「ARROWS S(EM01F)」、8月20日発売 端末代込みで月額4720円に:イー・アクセス、新サービス「EMOBILE 4G-S」を開始——「ARROWS S」発売に合わせて
端末代込みで月額4720円に:イー・アクセス、新サービス「EMOBILE 4G-S」を開始——「ARROWS S」発売に合わせて イー・アクセス、ソフトバンク網に対応した「ARROWS S(EM01F)」を発表
イー・アクセス、ソフトバンク網に対応した「ARROWS S(EM01F)」を発表 イー・アクセス、下り最大75MbpsのLTEエリアを全国に拡大 ただし3Gは下り最大21Mbpsに
イー・アクセス、下り最大75MbpsのLTEエリアを全国に拡大 ただし3Gは下り最大21Mbpsに イー・アクセスの「STREAM X」、7月25日からソフトバンクの3G網でも利用可能に
イー・アクセスの「STREAM X」、7月25日からソフトバンクの3G網でも利用可能に イー・アクセス、「STREAM X」のホワイトを7月18日に発売
イー・アクセス、「STREAM X」のホワイトを7月18日に発売 ソフトバンクとのシナジー効果も:イー・アクセスに聞く、月額3880円で使えるLTEスマホ「STREAM X」投入の狙い
ソフトバンクとのシナジー効果も:イー・アクセスに聞く、月額3880円で使えるLTEスマホ「STREAM X」投入の狙い



 背面にはHDMI出力やUSB端子がある
背面にはHDMI出力やUSB端子がある

 ボイジャー、電子書籍「ヒロシマ・ナガサキのまえに-オッペンハイマーと原子爆弾-」を発売
ボイジャー、電子書籍「ヒロシマ・ナガサキのまえに-オッペンハイマーと原子爆弾-」を発売



 Amazonのジェフ・ベゾスCEO
Amazonのジェフ・ベゾスCEO タブレットで変わる、学びのカタチ(3)
タブレットで変わる、学びのカタチ(3) タブレットで変わる、学びのカタチ(2)
タブレットで変わる、学びのカタチ(2) タブレットで変わる、学びのカタチ(1)
タブレットで変わる、学びのカタチ(1) 「コンプガチャ騒動」とは何だったのか(2)
「コンプガチャ騒動」とは何だったのか(2) 「コンプガチャ騒動」とは何だったのか(1)
「コンプガチャ騒動」とは何だったのか(1)

